コンサルティング会社に入ってよかったことは何か?と聞かれたら、私が真っ先に挙げるのは「どこでも使えるスキルが身についたこと」です。
中でも、情報を整理する力と、情報を引き出す力。
この2つはコンサルティング業務に限らず、どんな仕事でも使えます。
そして今、AI時代を迎える中でより重要になるのは、後者の「情報を引き出す力」かもしれません。
本記事では、私自身がコンサルとして働くなかで得たリアルな学びをもとに、これらのスキルがどう活きるのか私の考えを紹介します。
コンサルで身につく「2つの基盤スキル」
情報を整理する力(論理的思考能力)
コンサルの仕事は、とにかく膨大な情報に向き合うことから始まります。
クライアントからのヒアリング内容、社内資料、業界リサーチ、自分の過去の経験――
これらを無秩序に並べても、何の意味もありません。
そこで必要になるのが、情報を整理し、筋道立ててまとめる力です。
これはよく「論理的思考力」「ロジカルシンキング」と呼ばれるもので、コンサルタントが最も重視されるスキルのひとつ。
提案資料を作るときも、ただ情報を並べるだけではなく「なぜその提案が必要なのか」「どのような効果が期待できるのか」を一貫性のあるストーリーで示す必要があります。
このトレーニングを日常的に積めるのは、コンサルに入る大きなメリットだと思います。
こうした論理的思考を鍛えるには、書籍から学ぶのも効果的です。
特にコンサルなら誰もが一度は手に取る鉄板の2冊があります。
私自身もこの2冊を繰り返し読み込み、日々の仕事で何度も助けられました。
情報を引き出す力(インタビュースキル)
もう一つ、見過ごされがちですが非常に重要なのが「情報を引き出す力」です。
どんなに情報を整理する力が高くても、材料が足りなければ正しい結論は出せません。
クライアントとの限られた会議時間の中で、いかに本質的で一次的な情報を引き出せるか――これは成果物の質を大きく左右します。
そのためコンサルタントは、事前に徹底的なリサーチを行い、会議では「ネットで調べればわかること」は一切聞かない姿勢が求められます。
代わりに、相手が気づいていない潜在的な課題や、本音ベースの悩みを話してもらえるような質問を投げかける。
ここで鍛えられるインタビュースキルは、どんな業界でも使える普遍的な力になると考えています。
直接インタビュースキルを書いた本ではありませんが、クライアントとの会議において役に立つ内容が書かれている本を紹介します。
これらは、クライアント会議に限らず、日常の対話や営業場面でも役立つ内容です。
AI時代にこそ重要になるのは「情報を引き出す力」
論理的思考はAIに代替されやすい?
これまで「コンサルといえば論理的思考力」とよく言われてきました。
実際、情報を整理し筋道立てて結論を出す力は、どんな提案にも不可欠です。
ただ、近年はChatGPTをはじめとしたAIが、膨大な情報を瞬時に整理し、論理的な文章や資料のたたき台を作ることができるようになっています。
実際、多くのコンサルタントはChatGPTなどを使って業務を効率化しています。
つまり「整理する力」そのものは、AIに代替されやすい領域に入ってきているのではないでしょうか。
人間にしかできない「一次情報の発掘」
一方で、AIがどれだけ進化しても、クライアントが会議で語る本音や、社内資料に埋もれた課題を直接引き出すことはできません。
AIは既存の情報を再構成するのは得意ですが、ゼロから一次情報を掘り起こすのは苦手です。
だからこそ「情報を引き出す力」は、これからの時代にますます価値が高まると考えています。
相手の言葉に耳を傾け、的確な質問を投げかけることでしか得られない情報があるからです。
潜在的なニーズをどう引き出すか
さらに重要なのは、クライアント自身も言語化できていない「潜在的なニーズ」をどう引き出すか、です。
会話の中の違和感や、発言したそうな雰囲気、表情、矛盾している発言など、非言語情報をも拾い上げて深掘りできるのは、人間ならではの仕事。
このスキルは、AIを使いこなす時代だからこそ輝くと思います。
AIが整理した情報をもとに、コンサルタントがクライアントとの対話から本質的な課題を引き出す。
人とAIの役割が補完し合う未来では、まさに「引き出す力」が最大の武器になるのではないでしょうか。
※AI時代の人間の価値とは?について私の考えをこちらの記事で書いています。ご興味がありましたら是非ご覧ください。
キャリア全般で役立つコンサルのスキル
AI時代には「情報を引き出す力」の価値がさらに高まるとお伝えしましたが、もちろん論理的思考力も含め、どちらのスキルも他の業種や職種で役立つと考えています。
トラブル対応や課題解決に直結する
どんな仕事でも、想定外のトラブルやイレギュラーは必ず発生します。
業務マニュアルやルーティンだけでは解決できない場面で、コンサルで鍛えられた論理的思考力や情報整理力が大いに役立つと考えています。
例えば、システム障害が起きたときに「原因を分解して切り分ける」「どこから対応すべきか優先順位をつける」といった課題解決のプロセスは、コンサルの現場で叩き込まれるスキルです。
この考え方は業種を問わず、即戦力になるでしょう。
営業・システム改善など他業種にも転用できる
営業担当なら、顧客が抱えている課題を正しく引き出し、自社の商品やサービスがどう役立つかを筋道立てて説明する力が必要になるはずです。
これはまさにコンサルで培った「情報を引き出す力」と「整理する力」の応用だと思います。
また、システム部門なら、現場から寄せられる改善要望を整理し、優先順位をつけて解決策を提案することがあるでしょう。
これもコンサル経験がそのまま活きる典型的な例だと考えています。
つまりコンサルで学ぶスキルは、業界や職種を越えて“使える”力として転用できるのではないでしょうか。
コンサル経験で得られる成長機会
ここまで紹介してきたスキルも含め、私自身がコンサルで働いたことで得られたものは多いです。
その中でも「コンサルにいるとこういう経験ができる」とよく言われるポイントについても、やっぱり実際に身につくんだと感じました。
Excel・PowerPointを駆使した効率化意識
コンサルの現場では、常に「短時間で最大の成果を出す」ことが求められます。
そのため自然と、ExcelやPowerPointのショートカットを覚えたり、資料を効率的に作成する工夫を身につけました。
単に早く作業できるようになるだけではなく、「伝えるべき内容を正確に、余計な装飾は排してシンプルにまとめる」といった意識が醸成されたのも大きかったと思います。
こうした効率化やアウトプットの質へのこだわりは、他の仕事でも強みになると感じています。
若手のうちから大企業幹部と仕事する経験
もう一つ大きな特徴は、若手のうちから役職者や部長クラス以上の人と直接やり取りをする機会が多いことです。
若手のうちから自分より二十歳以上年上の方と議論を重ねる緊張感は、他の職場ではなかなか得られない経験でした。
当然、相手は新人かどうかに関係なく「プロのコンサル」として見てきます。
そのプレッシャーの中でアウトプットの質を求められる環境は、自然と自分の視座を高めるきっかけになったと思います。
多様な業界・企業文化に触れて広がる視野
さらに、プロジェクトごとに異なる業界や企業文化に触れられるのも魅力でした。
製造業からサービス業といった業界の違いはもちろん、同じ業界内でも会社によって特徴が違い、「なぜその会社がそういうやり方をしているのか」を考えることで、自分の視野も広がりました。
※もちろん、一つのクライアントの様々なプロジェクトを担当する、というケースもあるため、必ずしもいろんな会社を担当できる、というわけではありません。
一つの会社に長く勤めていると見えにくい“業界全体の動き”を体感できたのは、コンサルでの経験を通じてこそだと感じています。
AI時代を生き抜く「引き出す力」が養われる環境
「論理的思考」と「情報を引き出す力」はどこでも使える
私が考えるコンサルで鍛えられるスキルは、論理的思考と情報を引き出す力。
それと、ExcelやPowerPointなどのビジネス基礎スキルももちろん。
これらは、業界や職種を問わず、どんな場面でも使える力だと考えています。
日常のトラブル解決から、顧客対応、システム改善まで幅広く応用でき、キャリアを通して強みになり続けるはずです。
AI時代により重要になる「引き出す力」
一方で、AIが進化して論理的な整理や資料作成をある程度代替できるようになってきた今、人間にしかできないのは「一次情報を引き出すこと」だと私は思います。
クライアントの本音や潜在的なニーズを聞き出し、それをもとに課題を解決する力は、これからの時代にますます価値を増していくでしょう。
コンサルはスキルを磨く絶好の環境
こうしたスキルは意識すればどんな職場でも身につけられるものだと思いますが、コンサルは特に鍛えられる機会が多い環境でした。
限られた時間で成果を求められるプレッシャーや、多様な業界に触れる経験が、自分の成長を大きな後押ししてくれたと感じています。
最後にもう一冊、私が特に大きな影響を受けた「課題解決のバイブル」と呼ばれる本を紹介します。
もっと早く読んでおけばよかった、と後悔した本でもあります。
コンサルタントだけでなく、どんなビジネスパーソンにとっても課題解決の指針になる一冊です。
コンサルを目指す方、あるいはキャリアに迷っている方にとって、この経験を通して得られるスキルや視座は、将来の選択肢を広げる財産になるのではないでしょうか。
ここまで、私がコンサルティング業界を経験してよかった、と思えた理由である”身に着けられるスキル”についてお話ししました。
とはいえ、やはり良い面もあれば、自分には合わなかった、という面もありました。
こちらの記事で、その内容についてもお話ししていますので、ぜひ良い面と両面から見ていただけると嬉しいです。

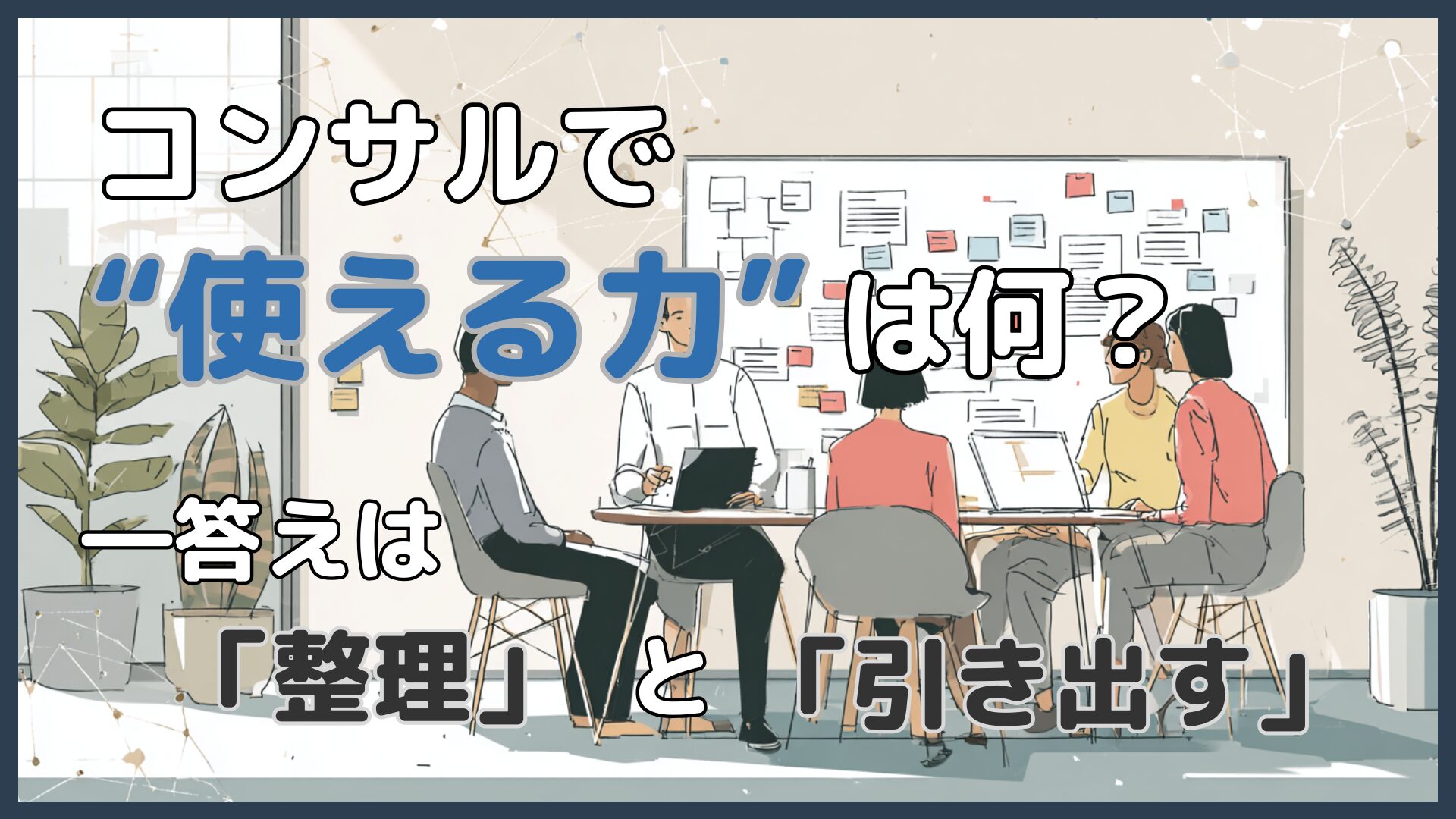

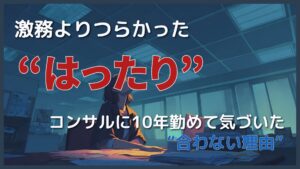
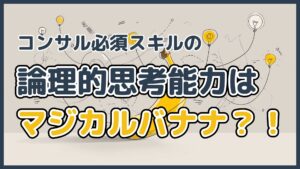
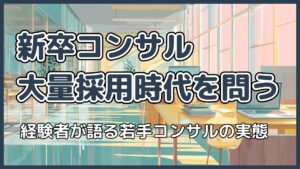



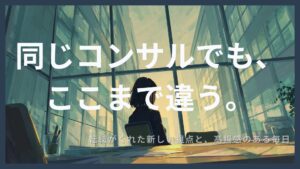
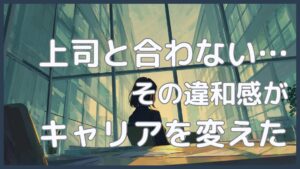
コメント