はじめに
職場において「上司との関係」に悩んだことがある方は、きっと少なくないと思います。私もそのひとりでした。
どれだけ頑張っても、自分が尊重されていないように感じる日々。そんな環境の中で、気づかぬうちに心がすり減っていた私がいました。
上司との関係については今振り返ると反省ばかりです。でも、その経験があったからこそ今の自分があります。
この記事では、私が上司との衝突を経て最終的に転職を選択した経緯を正直に綴ります。
今、当時の私と同じように上司との関係に悩んでいる方へ、少しでもヒントになれば嬉しいです。
上流フェーズにアサインされたときの高揚感
システム導入プロジェクトからの脱却と、新しい頭の使い方への期待
ひとつ前の記事で詳細に書いていますが、私がキャリアの初期に担当していたのは、システム導入のプロジェクトでした。
徐々に「これは本当にコンサルがやるべきことなのか?」と疑問を感じ始め、社内でアサイン変更(プロジェクトの変更)を申し出、上流フェーズ*のプロジェクトに関わることが決まりました。
*”上流フェーズ”というのは、システム導入よりも前の段階で”そもそもクライアントの課題は何か””どういった優先順位で課題に取り組むか””どのような解決策があるか”などを検討する段階のことです。
”システム導入”は”どのような解決策があるか”を検討した結果として出てくる解決策のひとつ、というイメージです。
今までとは異なる抽象度で物事を捉える必要があり、難しさもありましたがその新鮮さにワクワクしていました。クライアントの課題をゼロベースで考え、整理し、仮説を立てて提案していく──そんな頭の使い方に、自分の成長の兆しを感じていたのです。
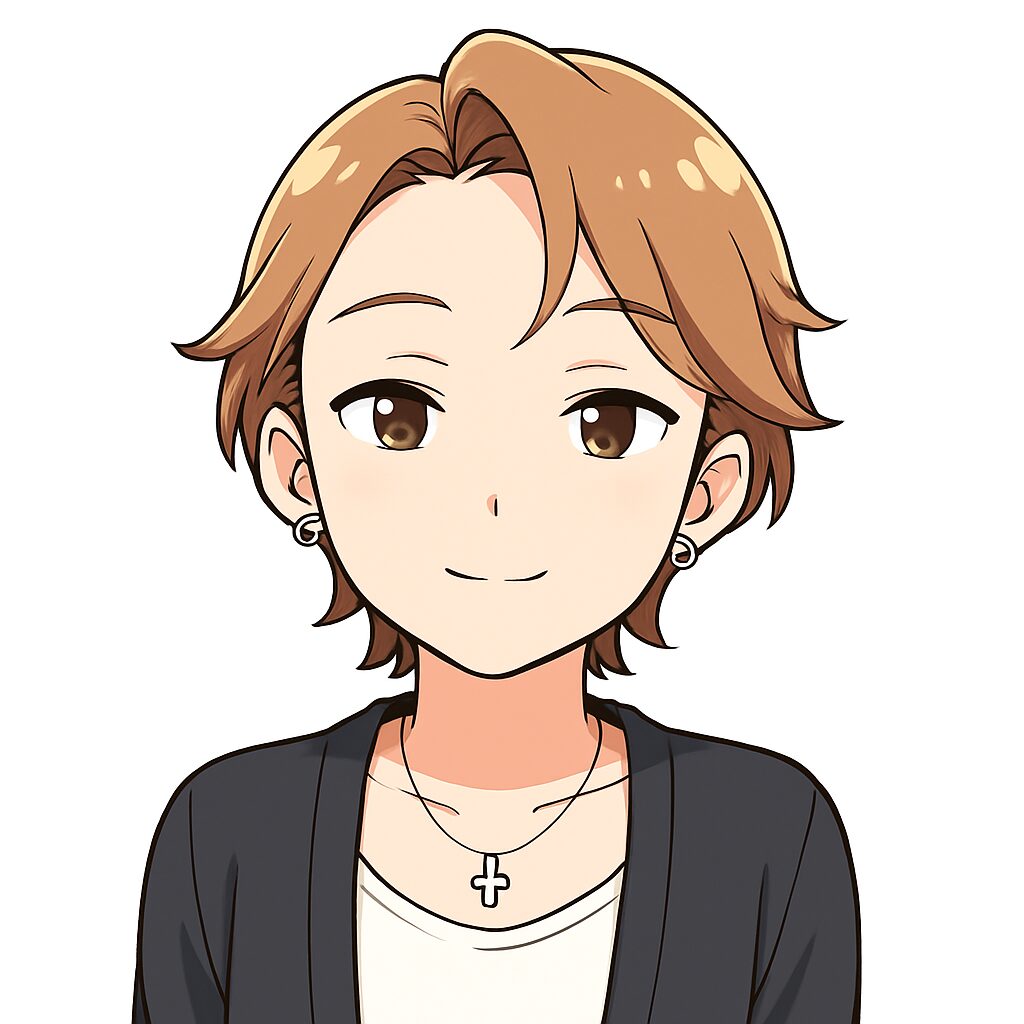
「新しいスキルを習得している感」に高揚感を覚えていた気がします
ただ、少しずつ「違和感」が芽生えてきます。
「私って、このプロジェクトに必要?」
プロジェクトそのものよりも、チームの中での自分の立ち位置や、上司との距離感に引っかかりを感じるようになったのです。
上司との衝突の日々
上司の裁量に圧倒された日々と、自分の無力さ
違和感の中心にあったのは、上司との関係でした。
その上司はとても有能で、プロジェクトにおける裁量も非常に大きく、クライアントとの信頼関係も確立されていました。
ですが、それゆえに、私が提案できる余地がほとんどありませんでした。
会議で発言してもスルーされる。資料を出してもほぼすべて上司の赤で書き直し。
自分のスキルが足りていないことはわかっていましたが、「私って必要なんだろうか」と感じてしまう日々が続きました。
理不尽というわけではない。でも、自分の手応えがまるでない。
何か貢献したいのに、そのチャンスが与えられないもどかしさ。そんな毎日に、私は少しずつ疲弊していきました。
あの頃の私は、正しさに固執しすぎていた──今思う“反省”
今思えば、当時の私の振る舞いには問題がありました。
私は自分の意見が通らないことに対して、上司を一方的に“聞く耳を持たない人”と決めつけていました。そして、「自分の方が正しい」と心のどこかで信じていたのです。
でも、今ならわかります。上司の視点からすれば、全体最適を見ながら、経験や判断基準に基づいて進めていたはずです。その中で、私の意見が採用されなかったからといって、それは「拒絶」ではなく「選別」だったのかもしれません。
正しいことを言っているつもりでも、それが相手に届かなければ意味がない。
「正しさ」よりも「伝え方」や「タイミング」、あるいは「信頼」の方が大切な場面がある。
そんな当たり前のことに、あの頃の私は気づけていませんでした。
視野の狭さと、“転職しかない”と思い込んだ理由
なぜあの時、転職という選択肢しか見えなかったのか
上司とうまくいかない。意見が通らない。存在意義が感じられない──。
そんな日々が続く中で、私は次第に「ここにいても、自分は成長できないんじゃないか」と思うようになっていました。
そして、もうひとつの思い込みに縛られていたことにも、今なら気づきます。
「この会社で上流フェーズをやりたいなら、この上司の下でやるしかない」
私がいる部署で、上流フェーズをやっている人はこの上司だけだと思ったからです。
でも、今思えばそんなことはありませんでした。社内異動という選択肢もあったし、冷静に上司と対話することで改善できる余地もあった・・・はず。でもその頃の私は、とにかく転職しか見えていませんでした。
そういった状況と、転職してみたい、という単純な興味が合わさって、転職を決意しました。



精神的にもかなり追い詰められていたんですよね……
転職活動と環境の選び直し
「上流工程を続けたい」を軸にしたコンサルファーム選び
転職を決意した私が会社を選ぶ際に考えた軸は、こんな感じです。
- 上流工程に”必ず”携われること=システム導入のサービスを提供していないこと
- 私がもともとかかわっていた領域に強い会社であること(クライアントの業種やプロジェクトの内容など)
- 年収が現状維持以上であること
- 福利厚生が最低限あること
上流工程にこだわったのは、上流工程での頭の使い方を習得して、システム導入で得たスキルと掛け合わせてより成長したいと思っていたからです。
また、私はシステム導入のキャリアが長かったこともあり、システム導入のサービスを持つ会社に入社したらきっとその関連プロジェクトにアサイン(配属)されるだろうと考えていたので、サービスとして提供していない会社を探しました。
「とにかく今の環境から離れたい」といった消去法ではなく「こういう環境で働きたいから、ここを選ぶ」という選択をしたのは、初めてだったように思います。
もちろん「完璧な職場」など存在しないという前提のもとで、それでも私は、自分の頭で考え、情報を集め、納得して選ぶというプロセスを大切にしました。(もちろん自分ひとりではなく、転職エージェントさんにも大変お世話になりました)
その結果、最終的に選んだのは、戦略ファームを標榜する新興のコンサルティング会社でした。
この経験は、私にとって「キャリアは自分で選び取ることができるのだ」という意識を持つきっかけにもなりました。
今振り返って思うこと
上司との衝突から得た学びと反省
あの頃の私は、たしかに未熟でした。
自分の正しさに固執してしまうことの危うさ。
関係性の中で、自分の立ち位置を客観的に見られなかったこと。
上司にすべてを投影してしまい、自分の課題から目を背けていたこと。
今思えば、社内の他のメンバーや上司以外の先輩に相談するという手段もあったはずです。
異動の可能性や、別のプロジェクトへのアサインを模索することだってできたかもしれません。
なんなら、自分の考え方を変えることだってできたでしょう。
でも、その頃の私は、視野が極端に狭まっていました。
それでも転職してよかったと思える理由
結果として、私は転職を選びました。
選択肢を一つに絞ってしまっていたという反省はありますが、それでも「自分の意思で環境を選び直した」という経験は、今の私にとって大きな意味があります。
それに「私でも転職できる」という自信にもつながりました。
他人に与えられたものではなく、自分で考えて選んだ道。
それがどんな結果になるにせよ、その選択に責任を持とうと思えるようになったのは、あのときの経験があったからです。
おわりに
上司とうまくいかない。意見が通らない。認められていない気がする──。
そんなふうに感じている方へ、この記事が届いてくれたらうれしいです。
キャリアにおいて、思い通りにいかないことはたくさんあります。
でも、だからこそ立ち止まり、自分の選択や振る舞いを見直す機会が訪れるのかもしれません。
もし今、上司との関係に悩んでいるなら、無理に耐える必要はありません。(パワハラ上司とかもいますしね)
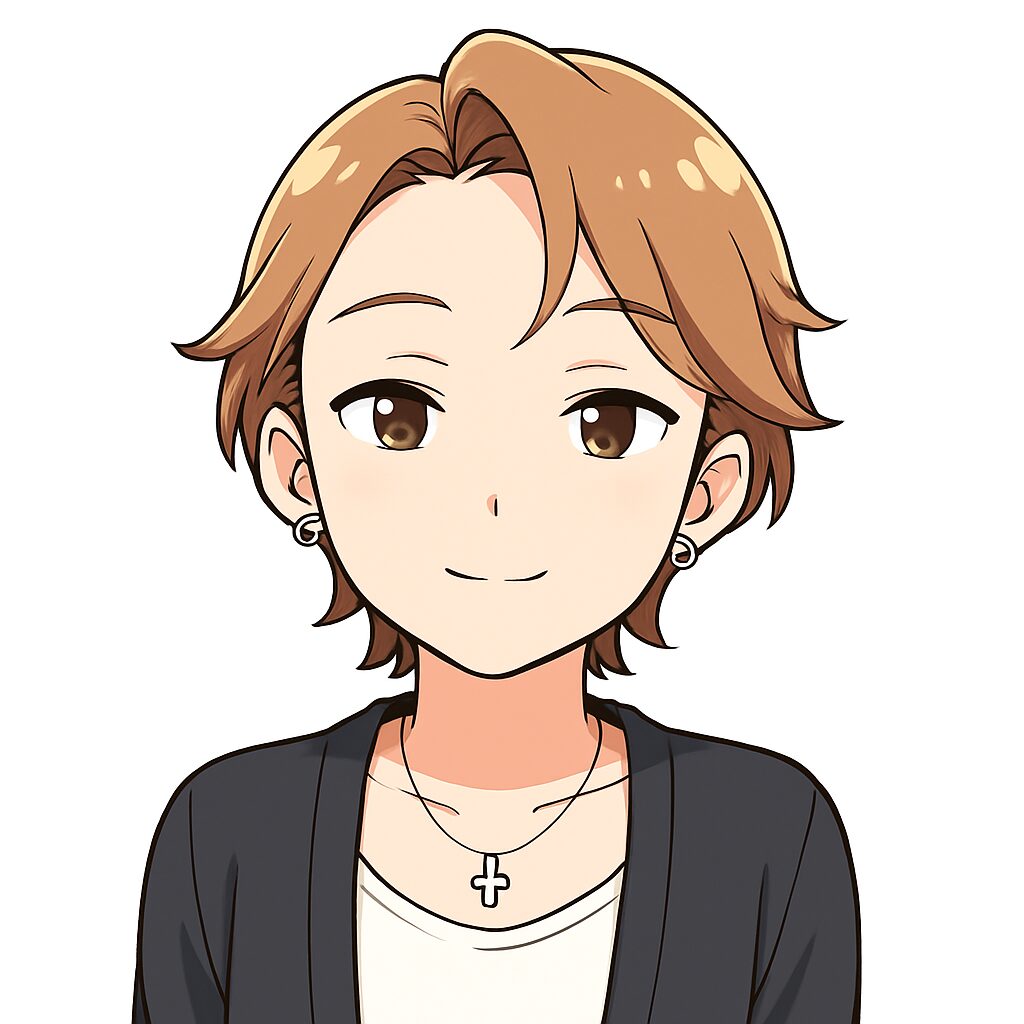
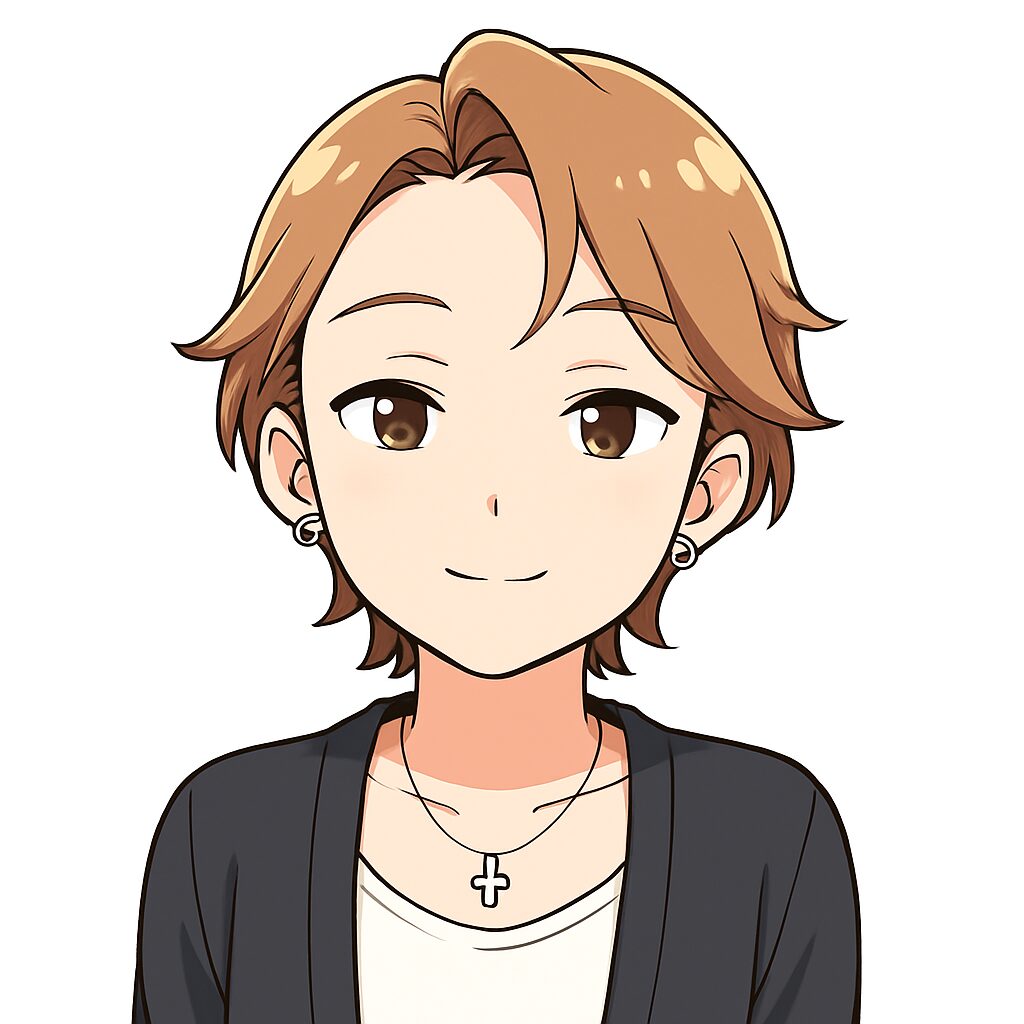
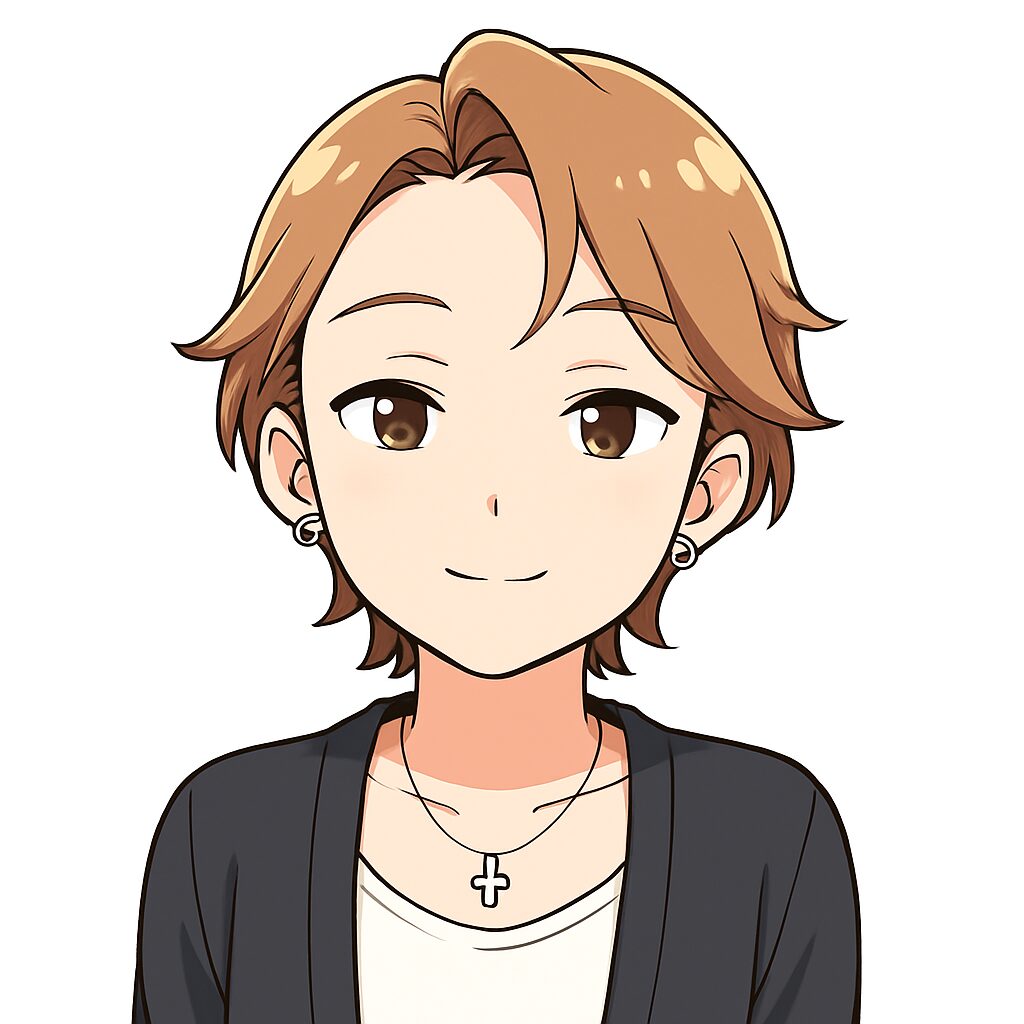
今後、職場での人間関係にフォーカスした記事も書いていければと思います。
ただ、環境を変える前に、自分で変えられることはないか、考えてみてください。
自分で変えられることはない、もしくは難しいなら、転職することは前向きな選択肢のひとつです。
あなたの選択が、あなた自身の納得につながることを願っています。
どんな選択をしても、その選択を”正解”にするのは、選択をした後の自分の行動ですから。(自戒を込めて)
次の記事では、転職してからのワクワク感を中心にお話ししていきます。お楽しみに!

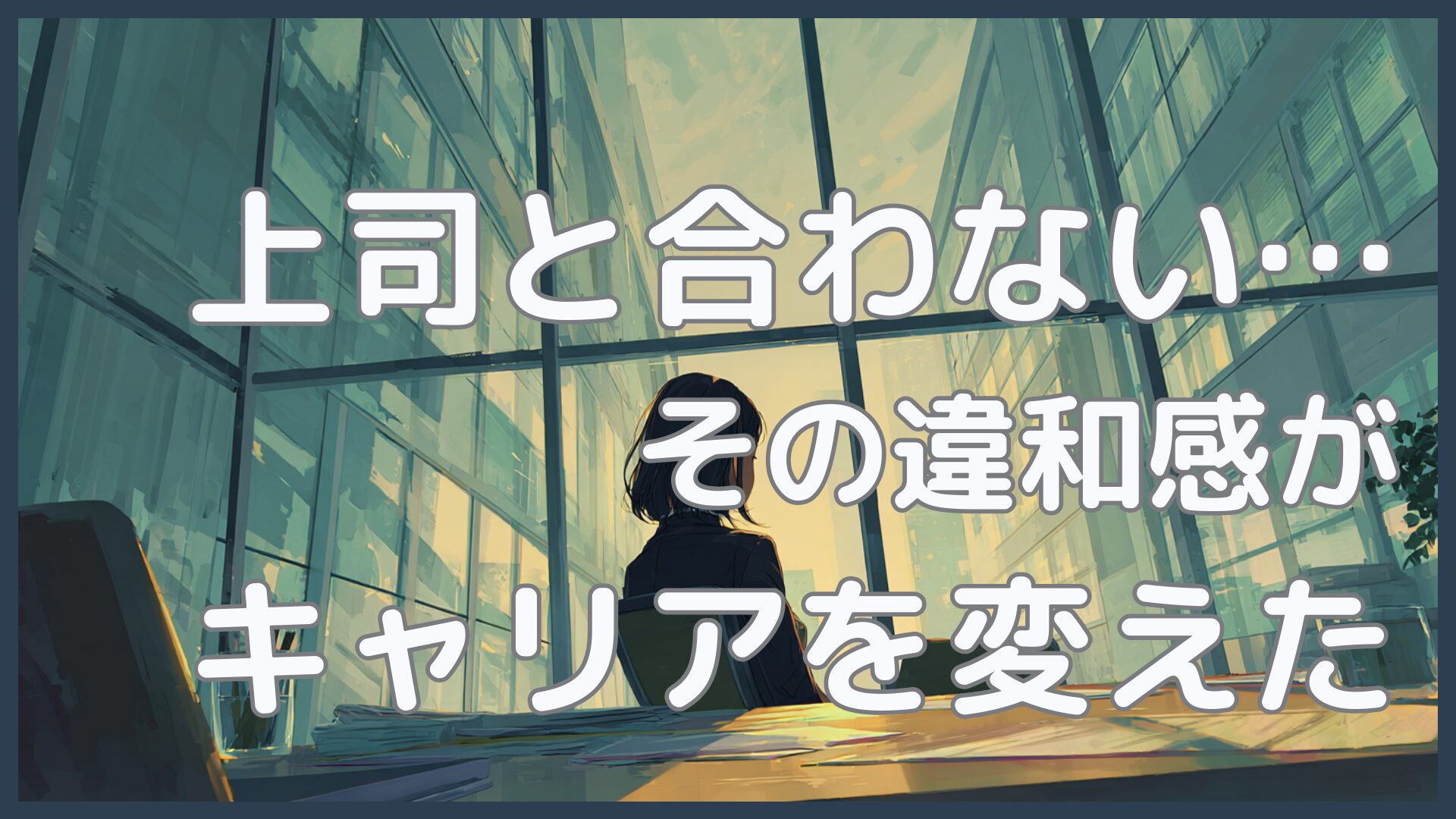
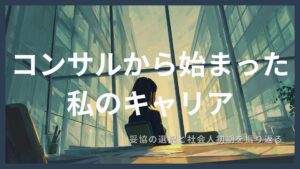
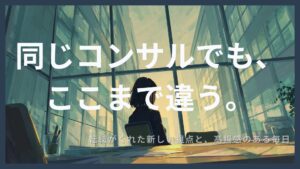
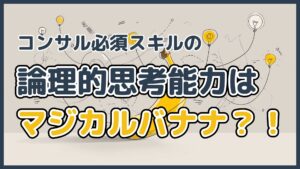
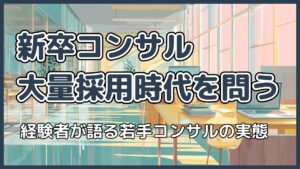
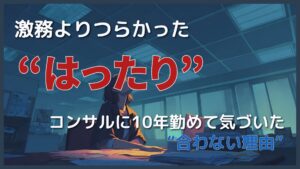
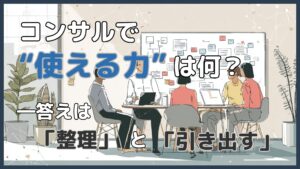



コメント