はじめに
やりたいことがわからないまま、「大学を卒業したら就職するものだ」と思い込んで社会に出た——それが私のキャリアの始まりでした。就職活動は本気になれず、自己分析も面接対策もほとんどしていません。そんな中で、成り行きでコンサルティングファームに入社することになりました。
この記事では、その妥協から始まったキャリアをどうにか正解にしようと走り続けた私の社会人初期を振り返ります。
いま迷っている誰かの参考になれば嬉しいです。
成り行きの就活と妥協の選択
就活に本気になれなかった理由
当時の私は、就職活動をどこか“他人事”のように捉えていました。周囲が自己分析やOB訪問、インターン、面接練習に取り組む中、私は「なんとかなるだろう」と構えていたのです。
今思えば、自分の人生に対して無責任だったと感じます。
しかも、「大学を卒業したら就職するものだ」という思い込みのもと、就職以外の選択肢を考えることもありませんでした。
中学を卒業したら高校、高校を出たら大学、大学を出たら就職——そんな“当たり前”を疑うことなく歩んでいたのです。

長期留学やワーホリという選択肢も考えてみたかったなぁ
コンサルティングファームに決めた“消去法”の背景
準備不足のまま臨んだ就活がうまくいくはずもなく、いくつか受けた企業では書類や一次面接で落ちました。
面接での受け答えや書類の内容が拙かったのだと思います。それでも「どこかは受かるだろう」と、現実から目をそらして対策をしませんでした。
そんな中で、ありがたいことに内定をもらえたのがコンサルティングファームでした。
コンサルタントの仕事も、その社会的な役割もほとんど理解していませんでしたが、他に選択肢がなかった私はそこに決めざるを得ませんでした。
いわば、妥協からのキャリア選択でした。
(ちなみに、当時はまだ“コンサル大量採用時代”ではありません)
コンサルキャリアのスタート——右も左もわからなかった新人時代
「基幹システムって何?」から始まった初プロジェクト
入社後に新人研修を受けた後、基幹システムの導入プロジェクトにアサイン(配属)されました。
研修でその概要を学んだものの、入社前は「基幹システム」という言葉すら知らず、当然プロジェクト内容もほとんど理解できていませんでした。
ロジカルシンキングやフェルミ推定など、コンサルにとって基本とされるスキルすら何のことやら状態。。。



正直、よく内定をもらえたなと思います……
ついていけない不安と、周囲への依存
毎日がわからないことだらけでした。それでも、目の前のタスクには必死に取り組み、先輩やクライアントの期待に応えたい一心でがむしゃらに働きました。
会議で発言できず、上司に「発言しないなら会議に出なくていい」と言われて泣いたこともあります。言われていないのに「期待に届いていないのでは」と不安になって落ち込み、よく泣きました。
そのたびに、先輩たちに励まされて何とか乗り越えていたと思います。
泣いては先輩たちに慰めてもらう、今思えばずいぶんと手のかかる新人でした。
(先輩たちありがとう)
(……ちなみに、中堅になってからもよく泣いてました)
少しずつ理解し、役割を果たせるようになった過程
仕事に慣れてくると、ようやく周囲の動きやプロジェクト全体の流れが見えてきました。
「このタスクは何に貢献するのか」「どうすればより良い資料になるか」「このプロジェクトは何のためにやっているのか」——そうした視点を持てるようになり、ものの見方が大きく変わりました。
会議で発言できるようになり、クライアントとの打ち合わせでファシリテーションを任される場面も増えていきました。
評価されるようになった一方で、生まれた違和感
クライアントとの関係構築と成果への実感
打ち合わせで存在感を出せるようになると、周囲の評価も変わっていきました。
「説明がわかりやすい」「レスポンスが早くて助かる」「次もあなたにお願いしたい」といったクライアントの言葉が励みになりました。
中でも、たった2週間常駐しただけのクライアントから感謝の品をいただいたときは、「何もできなかった私が認められた」と実感できた出来事でした。
また、上司から何度もストレートに「お前は優秀だから自信を持て」と言ってもらえたことも、大きな支えになっていたと思います。
「このシステム刷新、本当に意味があるのか?」という疑問
自信がつき視野が広がると、プロジェクト自体の“意味”に疑問を持つようになりました。
名目は「業務効率化」や「DX推進」でも、実際は「システムの保守切れによる入れ替え」にすぎないケースが多かったからです。
システムを入れ替えて「売上を向上させたい」のか「コストを下げたい」のか、そうだとしてその先は「新規事業に投資したい」のか「設備投資をしたい」のか、、、などが誰もわかっていなかったんです。
人間は変化に抵抗するものですし、その上「何のため」が明確でないプロジェクトにおいて、クライアントのメンバーからは現状維持以外の要件はほとんど出てきません。
クライアントが言っていたことを大雑把にまとめると「今のシステムと同じことができればそれでいいよ」でした。
それって、本当にコンサルタントがやるべき仕事なのか?
システム刷新の“先”を描くことこそ、コンサルの役割ではないのか?
そんな疑問が、常に心の中にありました。
正解の選択をするのではなく、選択を正解にする
今回は、就職活動から社会人としてのキャリアのスタートを振り返りました。
やりたいことが見つからないままの選択でも、入社後に努力を重ねることで、ある程度「正解」にできた部分があると思います。
もし今、やりたいことがわからない人も、まずは目の前のことに全力で向き合ってみてください。
そこから、少しずつ何かが見えてくるはずです。
次回は、感じた違和感に対して私がどう行動したかをお伝えします。
新しい挑戦への期待と、次第に訪れた息切れ感について、エピソードを交えながら綴っていきます。

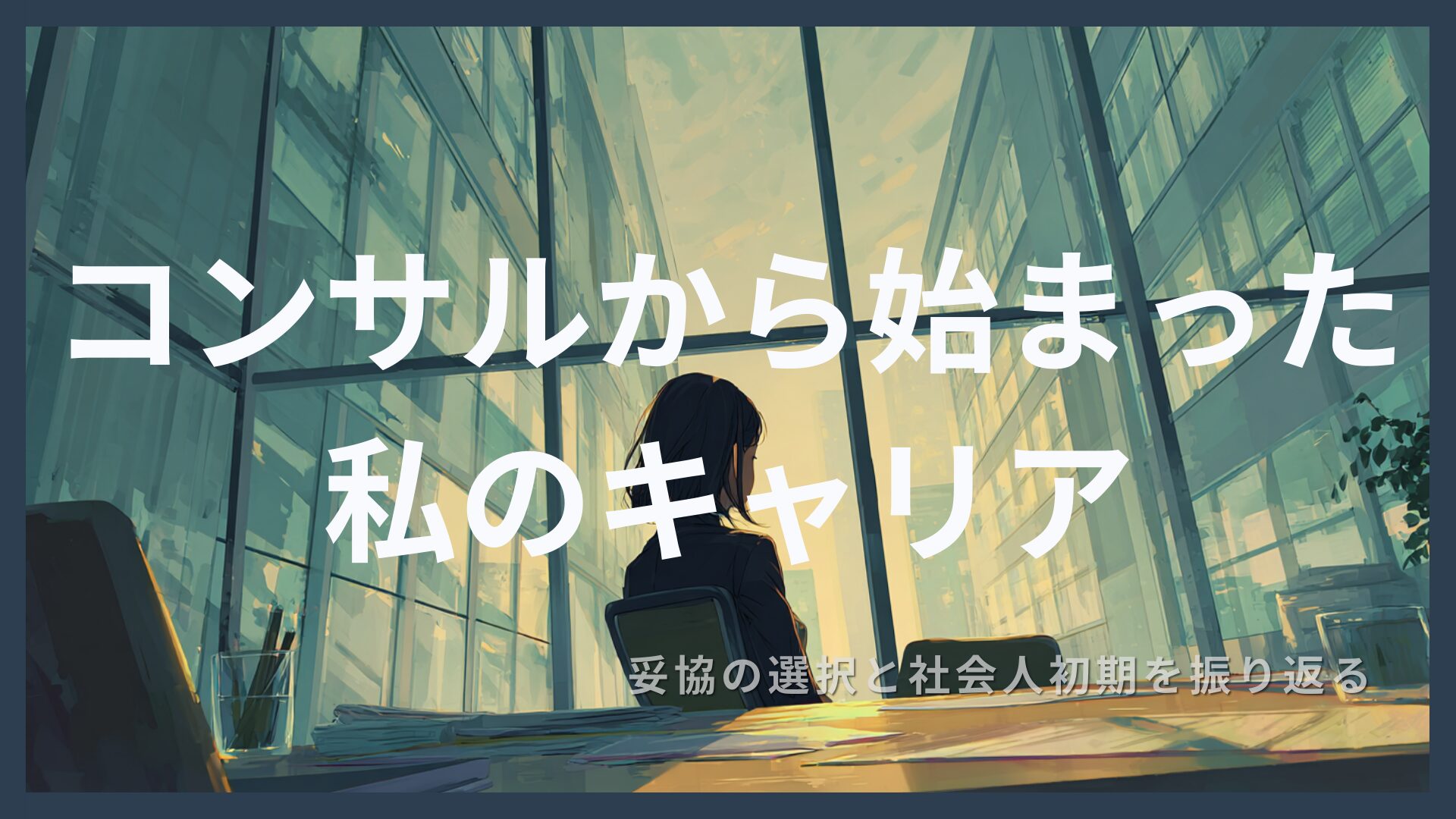
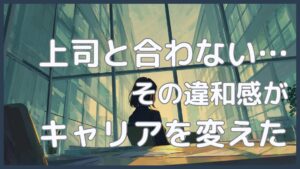
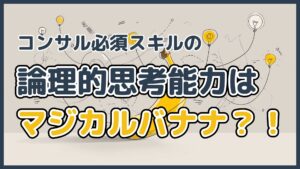
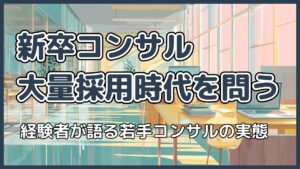
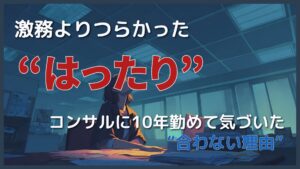
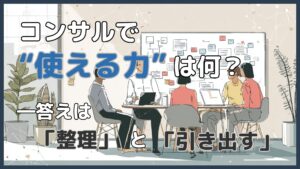



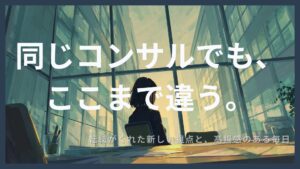
コメント