IELTSの勉強を始めると、多くの人がぶつかる壁がWritingとSpeakingです。
ListeningやReadingのように「正解」が一つに決まらず、テーマや試験官との相性によって結果が左右されるため、思った以上にスコアが安定しにくいと感じる人も多いでしょう。
私自身も3か月でIELTS7.0を目指す中で、一番苦労したのがこの2技能でした。
前編の記事では、ListeningとReadingの勉強法をまとめました。
形式に慣れること、アカデミックな単語を押さえること、過去問で実践を積むこと──これらがListeningとReading対策の鍵でしたが、WritingとSpeakingではさらに「型」を理解し、自分のアウトプットを磨くことが必要になります。
この記事では、私が実際に試行錯誤しながら取り組んだWritingとSpeakingの勉強法を、体験談を交えながら紹介します。
これから学習を始める方や、同じように壁を感じている方にとってヒントになれば嬉しいです。
WritingとSpeakingに共通する対策
ListeningやReadingと違って、WritingとSpeakingは「正解がひとつではない」という点が最大の難しさです。
さらには試験官との相性やテーマとの親和性にも影響を受けるため、努力がそのまま点数に直結しないと感じる人も多いと思います。
私自身も、この2技能ではかなり苦戦しました。
ただし、どんなテーマが来ても安定して答えられるようになるための“共通のコツ”があります。
出題の「型」を理解すること
WritingもSpeakingも、出題にはある程度決まったパターンがあります。
たとえば、WritingはTask1なら「グラフや図表の説明」、Task2なら「意見を述べるエッセイ」と枠が決まっていますし、Speakingも「自己紹介・身近な話題→特定トピックについての説明→ディスカッション」という流れが基本です。
まずはこの「型」を理解して、自分なりの回答パターンを作っておくことがスコアアップの第一歩になります。
パラフレーズとシノニムを意識する
同じ単語を繰り返すと減点対象になるため、「言い換え力」は必須です。
例えば “man” を “male” と言い換えるように、Synonyms(類義語)を意識的にストックしておくと表現の幅が広がります。
これはWritingでもSpeakingでも共通して効果を発揮します。
Synonymsは、IELTS向け単語帳の各単語についている類語などからインプットするといいでしょう。
私が使っていた単語帳はこちらです。
練習量と想定回答のストックがカギ
どんなに理屈を理解していても、実際に書いたり話したりする練習を重ねないとスコアは伸びません。
型を理解するためにも、答え方に慣れるためにも、たくさんの問題を解いてください。
これは、Listeining・Readingと同じです。
ストックを増やすためには参考書や過去問が欠かせません。
私が使っていたのはこちらです。
- Amazon | IELTS 17 Academic Student’s Book with Answers with Audio with Resource Bank (IELTS Practice Tests) | Cambridge University Press | Instruction
- Amazon | IELTS 18 Academic Student’s Book with Answers with Audio with Resource Bank: Authentic Practice Tests (IELTS Practice Tests) | Cambridge University Press & Assessment | Words & Language
- Amazon | IELTS 19 Academic Student’s Book with Answers with Audio with Resource Bank (IELTS Practice Tests) | Words & Language
- 【音声ダウンロード付】IELTSブリティッシュ・カウンシル公認 本番形式問題3回分 | ブリティッシュ・カウンシル, 旺文社 |本 | 通販 | Amazon
専門家やツールを活用した添削
Writing・Speakingは、自分では気づきにくい文法ミスや不自然な表現をしていることが多々あります。
IELTSの採点基準を熟知した専門家に添削してもらうのが理想ですが、最初のうちはChatGPTなどのAIを活用して、自分の書いた英文をチェックしてみるのも効果的です。
ChatGPTにIELTSの最新の採点基準を読み込ませて、自身の回答をチェックしてもらいましょう。
フィードバックを受けながら修正を重ねることで、少しずつ精度が上がっていきます。
Writingの勉強法
WritingはTask1とTask2に分かれていますが、どちらにも共通して大切なのは「いきなり書き始めないこと」です。
私は最初、構成を考えずに書き出してしまい、支離滅裂な文章や単語数不足で減点されることが多くありました。
そこで意識したのが、まずメモ用紙に構成をまとめてから書く習慣です。
構成があるだけで文章の一貫性が保て、余計な時間ロスも防げます。
構成メモを作る習慣
Task1なら「導入 → 全体の傾向 → 詳細の比較」、Task2なら「導入 → 理由1 → 理由2 → 結論」といった大枠を決めてメモに書き出します。
こうしてから文章を書き始めると、途中で迷走せず、必要な単語数も自然に満たせるようになりました。
Task1(グラフ描写)のコツと苦戦ポイント
Task1はグラフや図表を読み取り、それを正確に描写する問題です。
私はこの読み取りが本当に苦手で、「どこを説明すればいいのか?」と迷っているうちに時間がなくなり、雑な文章になってしまうことが何度もありました。
解決の糸口になったのは、模範解答を徹底的に研究することでした。
参考書に載っている解答例を読みながら「このタイプのグラフはこう説明する」とパターンを学び、徐々に自分の引き出しを増やしました。
Task2(意見エッセイ)の型とアイディアの出し方
Task2は、自分の意見を述べるエッセイ形式の問題です。
普段から考えたことのないテーマが出題されることも多いため、アイディアを素早く出す練習が重要になります。
ただし、難しい内容である必要はなく、論理が一貫していればシンプルな意見で十分です。
IELTSは”アイディアの難しさ”は採点対象ではありません。
無理に難しい内容にして変な英語になるくらいなら、シンプルで書きやすいアイディアにしましょう。
また、私は「①導入 ②理由1 ③理由2 ④結論」というシンプルな型を決めて使い回しました。
構成が固定されているだけで、考えるべきは「どんな理由を書くか」だけになり、ぐっと楽になります。
時間配分と効率的な練習法
Writingは時間との戦いでもあります。
アイディア出しやグラフの読み取りに時間をかけすぎると、文章を練る余裕がなくなってしまいます。
だからこそ、事前に型を決めておくことが大事なんです。
Writingでもっとも時間をかけるべきは”英語を書くこと”です。
正しい文法で書けているか、同じ表現・単語を何度も使いまわしていないか、など、スコアアップにつながるのはこの部分です。
ですから、参考書や過去問を使って構成やアイディアの型を作り、本番でも”英語を書く”ことに時間を使えるようにしましょう。
Writing用に私が使っていた参考書はこちらです。
Speakingの勉強法
Speakingは試験官と1対1で向き合う形式のため、他の技能とは違う緊張感があります。
限られた時間で自分の考えを英語で伝えるのは、思っている以上にエネルギーを使います。
私にとっても大きな壁でしたが、以下の工夫で少しずつ安定して答えられるようになりました。
英語を話すことに慣れるのが第一歩
試験本番では「英語を話すこと」に集中できるかどうかが大きな分かれ目になります。
英語を話すこと自体にエネルギーを使っていると、緊張と相まって言葉が出てこなくなるからです。
私はもともと1年間TORAIZで英会話を勉強していたため、英語を話すことのハードルは低かったため、ここは最初からクリアしていました。
今、英語を話すのに慣れていない人は、ぜひオンライン英会話などを活用し、とにかく「英語を口にすること」を日常化してみてください。
試験対策だけでなく、英語で会話する習慣そのものがSpeaking力の土台になります。
よく出るトピックと想定回答の準備
IELTSのSpeakingは「自己紹介・身近な話題 → トピックカードでのスピーチ → ディスカッション」という流れが決まっています。
参考書を見れば頻出トピックが分かるので、事前に想定回答を用意しておくのが効果的です。
たとえば「好きな映画」「最近読んだ本」「教育やテクノロジーに関する意見」などはよく出るテーマです。
短いフレーズでも用意しておくと、本番で安心感があります。
Speaking対策で私が使っていた参考書はこちらです。
シンプルに答える意識と失敗から学んだこと
私が失敗していたのは、緊張からついダラダラと話しすぎることでした。
質問の意図から外れた答えになってしまい、スコアが伸び悩んだのです。
逆に、話すのが苦手な人は極端に短い答えになってしまうかもしれません。
大事なのは「質問にシンプルに答えること」。
その上で、理由や具体例を一つ加えるだけで十分評価されます。
まとめ
WritingとSpeakingは、ListeningやReadingに比べて「正解が一つに決まらない」ぶん難易度が高く、私にとっても大きな壁でした。ただし、出題には共通の「型」があり、それを理解して繰り返し練習すれば、スコアは着実に伸ばせます。
特に意識したポイントは次の3つです。
- 型を理解すること(構成や回答パターンを決めておく)
- パラフレーズ力を磨くこと(同じ単語を繰り返さず表現の幅を広げる)
- 数をこなし、想定回答をストックすること
さらに、専門家やツールのフィードバックを受けながら改善を続けると、自分では気づけない弱点を補強できます。
WritingとSpeakingは、慣れないうちは苦しく感じるかもしれませんが、型をベースに地道な練習を重ねれば、必ず結果につながります。
私もこの方法で3か月で7.0を達成できました。
この記事が、同じように挑戦している方の背中を少しでも押せたら嬉しいです。
※社会人がどのように英語を勉強する時間を捻出したのか?習慣化の仕組みについてはこちらの記事もご覧ください!





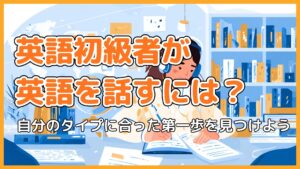



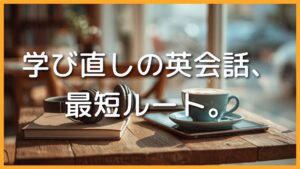
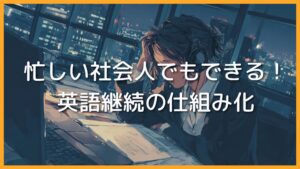
コメント