コンサルティング業界は「圧倒的成長」や「高収入」といった華やかなイメージで語られることが多いかと思います。
就活生や転職希望者の中には、憧れを持っている人も少なくないはずです。
私は約10年間コンサルタントとして働きましたが、その中で「この業界の会社で働くのは、私には合わないな」と感じ、退職しました。
激務そのものよりもつらかったのは、“自分の信念に反する提案をしなければならないこと”や、“経験不足を補うために、はったりをきかせてクライアントを納得させなければならないこと”でした。
もちろん、これはあくまで私個人の意見であり、人によっては全く違う見方もあると思います。
この記事は、一人の元コンサルの体験談として読んでもらえたら嬉しいです。
私がコンサル業界で感じた違和感
提案のための提案をしなければならない現実
コンサルティングという仕事は、本来クライアントの課題を整理し、クライアントにとって最適な解決策を提示することに価値があります。
コンサルティング会社の理念にも必ずといっていいほど「クライアントファースト」と書かれています。
ところが現場に立ってみると、「本当にクライアントのためになるのか?」と首をかしげるような提案をせざるを得ない場面が少なくありませんでした。
会社としての売上や評価指標が優先される場面も多くあり、特に売上規模の大きいシステム導入案件は会社にとって魅力的で、必要な前段階の検討(戦略やKPIの議論など)を飛ばしてでも契約を取りにいく姿勢が見え隠れしました。
もちろん、会社もビジネスとして利益を出さなければなりません。
その理屈は理解できるものの、「本当にクライアントのためになっているのか」という自問が消えることはなく、次第に心が疲弊していきました。
経験不足を補う“はったり”のプレッシャー
コンサルティングビジネスへの違和感だけでなく、自分自身の経験に対する自信のなさも、違和感につながりました。
新卒からコンサルとして働き始めた私は、現場の実務経験や専門知識が十分にあるわけではありませんでした。
それでもクライアントの前では「プロの専門家」として振る舞い、納得感のある提案をしなければならない――。
このプレッシャーは非常に重く、時に「知ったかぶりをしているのではないか」という罪悪感に苦しみました。
もちろん、チーム全体や会社含めて知見を補完しながら進めてはいましたが、個人としての未熟さを隠さなければならない状況は、精神的にきついものでした。
激務よりもつらかったこと
長時間労働の厳しさは覚悟していた
コンサル業界が激務であることは、入社前から覚悟していました。
朝から深夜までの勤務、休日の作業、突発的なトラブル対応――こうした働き方は決して楽ではありません。
でも、特に若手のころは、自分の成長そのものがモチベーションになっていたので、多少の無理は「修行」と割り切ることもできました。
実際、時間的な負担そのものは、ある程度耐えられるものでした。
納得できないサービスを提供するしんどさ
ただ、本当に辛かったのは「自分が何をやっているのか」に納得できなかったことです。
例えば、私が多く担当していたのはシステム導入案件でした。
本来であれば、システムを入れる前に「会社としてのビジョンは何か」「経営層がどんなKPIを目指すのか」を明確にし、それを部門や現場レベルにブレイクダウンしていく必要があります。
そのプロセスを経て初めて「この目標を達成するためにはこういう業務が必要である」「その業務にはこのシステムが必要だ」「このシステムはシステム部門が担当するべき」「こっちは各部門が担当するべき」といった最適な役割分担が見えてくるはずです。
ところが、実際の現場ではそうした前提をすっ飛ばして「とにかくシステムを入れること」が目的化してしまうケースが少なくありませんでした。
なぜなら、長期契約で売上が大きく見えるシステム導入は、コンサル会社にとって魅力的である場合があるからです。
クライアントの課題に本当に向き合うよりも、会社の数字が優先されているように感じる場面が多々ありました。
そんなプロジェクトに参画すると、私は「この案件って、クライアントにとって本当に意味があるんだろうか?」「多額の費用と人的リソースを投じてまでやる価値があるのか?」と自問せざるを得ませんでした。
クライアントが求める機能が、実は導入予定のシステムでは実現できないと気づいても、それを根本から問い直すことは難しい
結果として「やるべきことをやらずに形だけ整える」提案に加わってしまうこともあり、納得感を持てないまま進めざるを得ない日々が続きました。
激務の時間を投じているにもかかわらず、自分の信念と矛盾する仕事をしている――その虚しさこそが、私にとっては肉体的な疲労以上に大きな負担となっていきました。
罪悪感との付き合い方
さらに、経験不足を隠してクライアントに“専門家”として向き合わなければならない状況は、常に罪悪感を伴いました。
もちろん自分なりに勉強したり、先輩方から情報を集めたり、もちろん少なからず自分の経験もありましたが、「自分は本当にこの金額に見合う価値を提供できているのか?」という問いが頭から離れませんでした。
周囲の先輩たちが当然のようにこなしていく姿を見て、「自分が弱いだけなのか」と自責する日々もあり、この罪悪感と折り合いをつけることが何より苦しかったのです。
それでも得られたこともある
ここまで主に「私がコンサルティング業界に合わなかった部分」について書いてきましたが、もちろんコンサルの経験を通じて得られたスキルや学びも確かにあります。効率化の工夫や、多様なクライアントとの関わりを通じて身についた力は、今も自分のキャリアに生きています。
ただ、これらについては一つの記事で語り尽くすには収まりきらないので、詳しくは別の記事でまとめています。興味のある方は、ぜひこちらも読んでみてください。
私にとっての結論――コンサルは「合わなかった」
向いている人・やりがいを感じられる人
コンサルの仕事に強いやりがいを感じられる人は確かにいます。
例えば、プロジェクトによるクライアントの成果を自分の成果と捉えられる人、または「高収入や成長スピード」という報酬に明確なモチベーションを持てる人です。
納期や期待値に追われながらも、それを力に変えられる人にとって、コンサルは刺激的で魅力ある職場だと思います。
向いていない人・私が合わなかった理由
一方で、私のように「自分が納得できるサービスを提供できているか」に強くこだわるタイプにとっては、苦しい場面が多いかもしれません。
経験不足を“はったり”で補うことへの罪悪感、会社都合とクライアントファーストの間で揺れる矛盾、プロジェクトの意義そのものに疑問を抱きながら進める虚しさ――これらが積み重なり、私は「コンサル業界は自分には合わない」と結論づけました。
「合わない」と気づけたことの価値
ただし、ここで強調したいのは「コンサル=悪い業界」ではない、ということです。
あくまで私個人の意見であり、人によっては全く違う景色が見えるはずです。
大切なのは、自分に合っているかどうかを見極めること。
私は約10年働いた末に「合わない」と気づけたことで、自分のキャリアを次のステージに進める判断ができました。
迷いながらでも働く中で、自分に合う/合わないを知ること自体が、大きな意味を持つのだと思います。
おわりに
これからコンサルを目指す人へ
コンサル業界は確かに厳しい環境ですが、得られる経験やスキルは大きな価値を持ちます。
私には合いませんでしたが、そこで培ったことが次のキャリアに役立っているのも事実です。
これから目指す方は、ぜひ現役だけでなく、辞めた人の声にも耳を傾けながら、自分に合うかどうかを多角的に判断してみてください。
今コンサルで悩んでいる人へ
もし今コンサルの仕事に違和感やつらさを感じているなら、それはあなただけではありません。
業界の性質上、向き不向きがはっきり出やすいからです。
私自身も「合わない」と思ったからこそ退職を選びましたが、その選択を後悔していません。
キャリアの選び方に「絶対の正解」はないからこそ、自分が納得できる道を選ぶことが一番大切だと感じています。

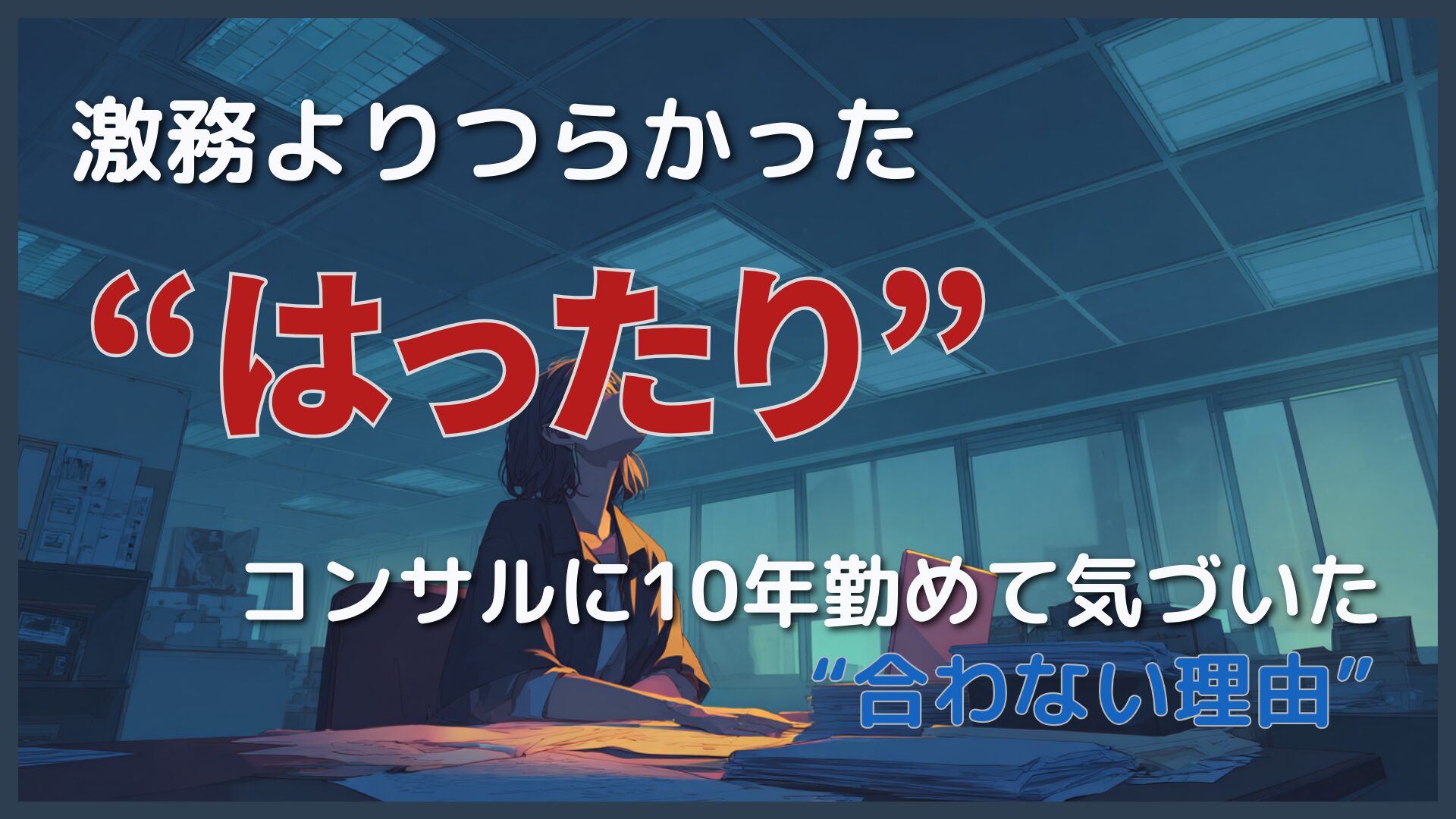
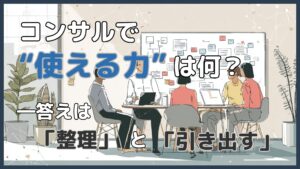

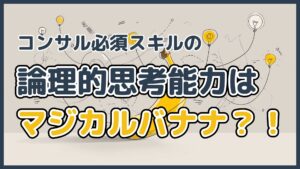
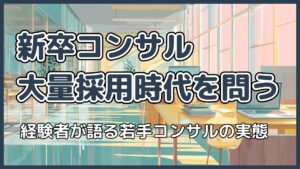



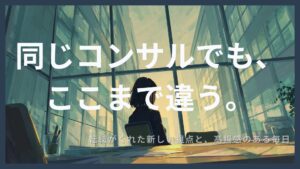
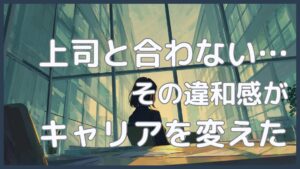
コメント