AIが提示する答えは一見すると論理的に正しそうですが、実は重要な情報や前提条件を見落としているケースがあります。
その情報をそのまま鵜呑みにすれば、思わぬ失敗につながりかねません。
そこで必要になるのが「論理的思考力」とその基礎となる「知識」です。
この記事では、私自身がAIを活用する中で感じた、この両方を使って妥当性を確かめることの重要性を紹介します。
AIは、使う側の人間の「論理」と「知識」が揃ってはじめて、本当の意味で役立つのです。
AI時代に改めて考える論理的思考力
私がコンサルで感じた論理的思考能力の重要性の相対的な変化
以前の記事で、AI時代のコンサルティングの仕事は、論理的思考能力よりも情報を引き出す力のほうが重要になりそうだ、ということを書きました。
実際に、情報を論理的に整理したり、提案のストーリーを作る際にはAIの力を存分に使うことができ、その部分で使っていた「論理的思考能力」は以前と比較して使う場面が限定されたように思います。
とはいえ、AIを使うから論理的思考能力が不要、という意味ではありません。
むしろ、以前より高度な論理的思考能力が必要になっていると思います。
それでもAI活用に論理的思考能力が必須だと考える理由
AIが広く使われる今、論理的思考能力の必要性はむしろ高まっています。
AIはまるで全知全能のような、一見するとなるほどと納得してしまうようなもっともらしい答えを提示します。
でも、それが本当に論理的におかしくないのか、妥当なのか、を判断できるのはAIを使う人間で、そのためには論理的思考能力が不可欠だからです。
コンサルという、もともと「論理的思考能力」がフィーチャーされていた環境においては相対的に使う場面や重要性が限定されているように見えても、AIを使いこなす上で論理的思考能力は必須だと考えます。
AIの出力に潜む落とし穴と精査の必要性
一見正しそうに見える危うさ
AIの提案は筋道立っているように見えても、よく見ると前提が抜け落ちていたり、条件が現実と合わないことがあります。
例1.私がボディメイクの計画をChatGPTに相談したとき
ChatGPTをプロのパーソナルトレーナーに見立て、いつまでにこういう体型・体重・体脂肪率になっていたい、ということを伝え、日々の食事・運動管理をしてもらうことにしました。
歩数が少ない日は有酸素運動を取り入れたり、体組成計測の結果を分析して上半身強化のメニューを提案してくれたりと、一見するとそれらしい管理をしてくれています。
ですが、ある日、「肩を鍛えるために、アームカールか、膝付き腕立て伏せをしましょう」と言われました。
その時私は、「アームカールと膝付き腕立て伏せって、鍛えられる部位違うよね?」と疑問に思い、ChatGPTに聞き返したところ、「その通りです!あなたには膝付き腕立て伏せのほうがおすすめです!」というようなことを言われました。
この例では、ChatGPTが言ったことは厳密に言うと間違いではありませんが、誤解を招く表現をしています。
これがビジネスの場面だとどうでしょうか。
例2.クライアントから「売上を上げたい」と言われたとき
ChatGPTに「この業界の、この会社(※秘密保持契約等に抵触する可能性があるので、ChatGPT等に固有名や固有情報を入力する際は慎重に検討してください)が、売上を向上させたい、と言っている、どうしたらいいか」と聞き、ChatGPTが「それでは新商品を開発すればいいでしょう。新商品の発売は話題性もあり、売上の向上が見込めます」と答えたとします。
確かに、一時的には売上が上がる可能性はあるでしょう。
でも、長期的に見たらどうでしょうか。新商品の開発にリソースを使うことで既存商品の改良等にリソースを割けず、既存商品の売上が下がるかもしれません。
また、売上は上がるかもしれませんが、新商品開発のためにコストを使うことで利益が下がるかもしれません。
この例は極端な例ですが、AIが必ずしも最善の策を提案してくれるとは限りません。
「AIは完全ではない」と知ること
AIの答えが「表面的には妥当そうに見える」のは、AIを使う人間にとっては大きな落とし穴です。
だからこそ、その事実を知り、AIが提供する情報の整合性を人間が確かめる必要があります。
そうでなければ、間違った方向に進んでしまったり、不必要に遠回りしてしまう可能性もあるでしょう。
提案の背後にある論理を推測し、知識と照らし合わせて「本当に妥当か」を確認する。
このプロセスを怠ると、AIは強力な味方ではなく、誤解を広げる存在になりかねません。
危うさを見抜くために必要なもの
高度な論理的思考能力
危うさを見抜くには、単なる直感ではなく、高度な論理的思考が求められます。
AIの提案は、何度も言うように「一見正しそう」に見えます。
論理的整合性を普段から気にしているコンサルでさえ、鵜呑みにしてしまうことすらあります。(鵜呑みにすることがすべて間違いだ、というつもりはありません)
だからこそ、一見論理的に正しそうなことを、一歩引いて再検討する癖をつける必要があります。
AIから何か情報を提供された際、その情報について「前提は正しいか」「因果関係は適切か」「自分が知っている知識と整合性が取れるか」「見落としている観点がないか」といった点を確認する力が必要です。
そのために有効な思考法が、仮説思考です。
「この前提で考えるなら、こういう答えになるはずだ」ということを事前に検討しておき、AIの情報と照らし合わせて、AIのおかしな部分・はたまた仮説のおかしな部分を見つけるのです。
事前にあたりを付けておく、とでも言いましょうか。
仮説思考については世の中にたくさんの本が出ていますので、そちらを改めて読んでいただくのが良いかと思いますが、私のおすすめはこちらです。
最終的に提示する案が妥当かを判断するのは、どんなにAIが発達しても人間なのです。
前提となる知識
さて、ここまでは論理的思考能力について話をしてきましたが、その論理的思考能力を裏から支えるのは知識です。
2つの例を上段で出しましたが、どちらも知識がなければ指摘できません。
筋トレであれば、この筋肉に効かせるためにはこういう動きが必要だ、など。
ビジネスであれば、簿記の知識、サプライチェーンの知識、国や業界ごとの慣習など。
こういった背景知識があってこそ仮説を立てられるし、AIが出してくる提案内容に対して、「おかしいのでは?」と疑問を抱くことができるのです。
だからこそ、論理的思考能力というある種のテクニックだけでなく、その基盤となる知識を付けることが、これからのAI時代であっても大事だと言えるでしょう。
知識があってこそ、論理的思考は真に力を発揮し、AIの出力を適切に評価できるのです。
AIと向き合う人間の姿勢
鵜呑みにせず疑問を投げかける
AIの提案については、常に批判的な視点を持って向き合う必要がある、と心に刻むことが大切です。
毎回、「この回答は妥当か?」と問い直しましょう。
そのために、知識を付けることも忘れないでください。
もちろん、その知識を付けるのにAIを使ってもいいと思います。
その際に出典を提示させることにより、その正確性を担保することもできます。
その上で、違和感を覚えたら再度問いかけ、前提や条件を確認する。
こうしたやり取りによって、AIの出力はより精緻になり、人間にとって実用的なものへと近づきます。
AIを補助として位置づける
また、AIは人間を置き換える存在ではなく、あくまで補助ツールである、という意識も大切です。
AIが出した答えをそのまま採用するのではなく、自分が、自分の目的や判断基準に照らして最終判断を下すのです。
AIを使う側であり続けるには、この距離感を忘れないことが大切です。
人間がAIに支配されないために
AIは、人間の生活において強力なツールです。
様々な作業を効率化してくれたり、一人でもブレインストーミングができる良き相棒でもあります。
ですが、AIはあくまでもツールであり、全知全能の神ではないということを肝に銘じ、そのAIを最大限利用するためには、それを使う人間が知識をつけ、その知識をもとに論理的思考能力を鍛える必要があります。
AIを無批判に受け入れれば、人間がAIに使われる世界になりかねません。
そんな未来を防ぐためにも、人間はAIを使う側であり続ける必要があり、そのためには人間が知識と論理的思考能力を付け続ける努力が必要です。
そうして初めて、人間はAIに使われるのではなく、人間がAIを使い、人間の生活を豊かにしていけるのだと思います。
AIがAIを作るシンギュラリティの時代における人間の価値について、別視点からの私の考えをこちらの記事で書いています。
こちらも併せてお読みいただけますと幸いです。

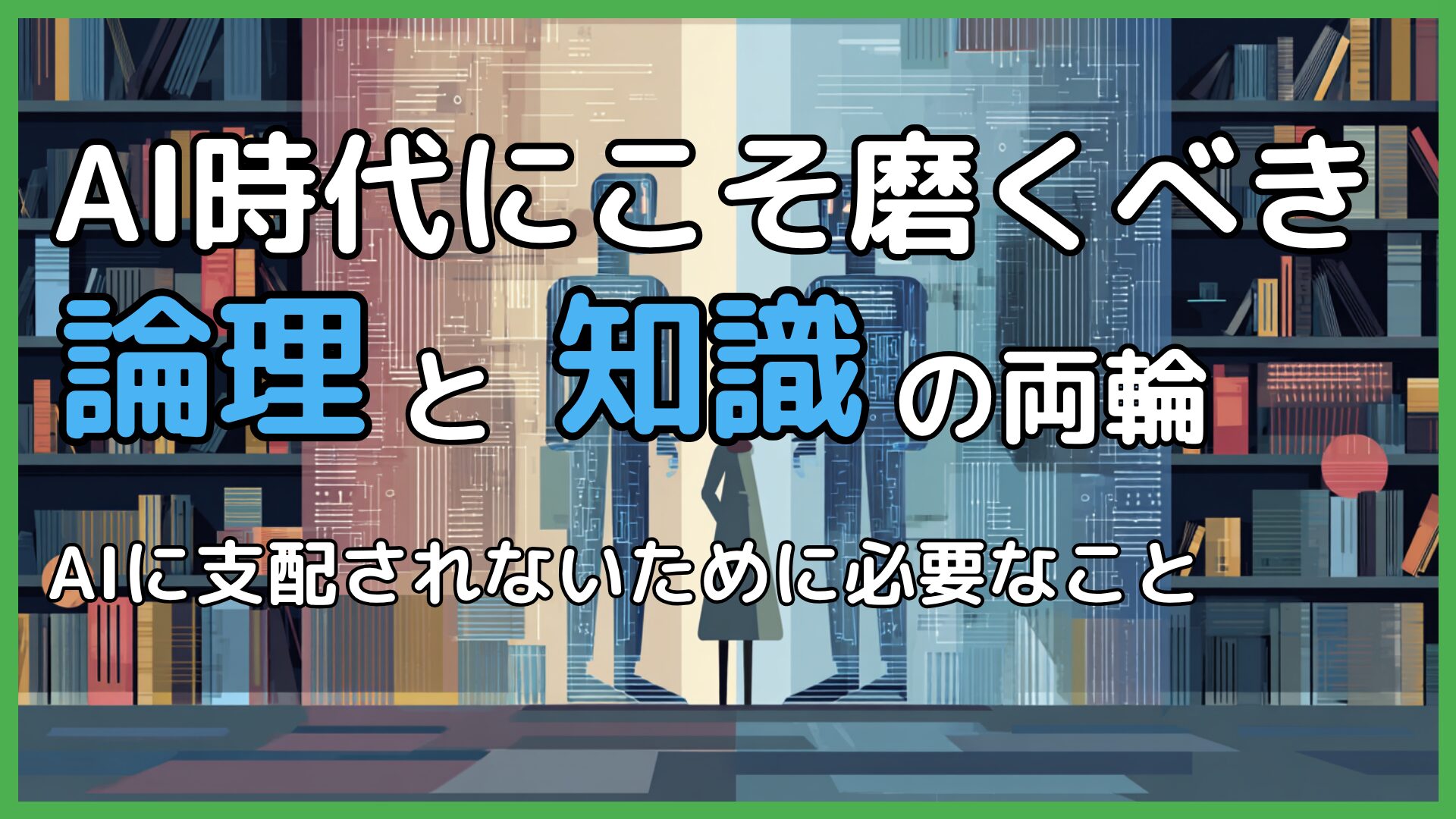
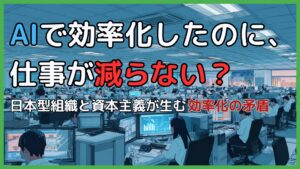

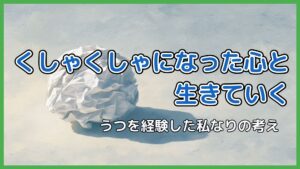



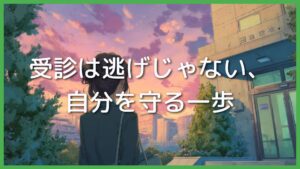
コメント